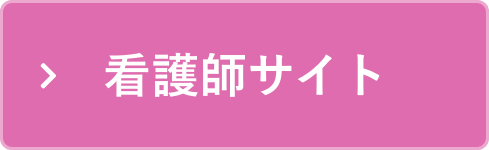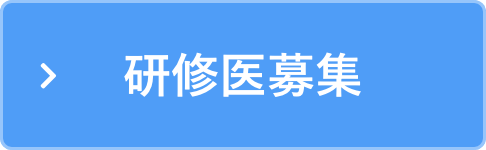診療科・部門・センターのご案内
- トップページ
- 診療科・部門・センターのご案内
- 耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科
診療科の特徴と診療内容
大手前病院耳鼻咽喉科では、耳鼻咽喉科、頭頸部外科領域の疾患に対して、迅速に診断・治療まで至ることを心掛けています。当院では検査体制が充実しており、小児聴力検査を含むあらゆる聴力検査・めまい検査(ENG・VEMP・蝸電図)・補聴器装用判定・耳鳴に対するTRT療法・味覚検査・嗅覚検査などを速やかに施行することで、速やかな診断に結びつけています。さらに近年問題となっております嚥下障害に対しても、原因を積極的に精査し、入院のうえで理学療法や手術療法を行い、嚥下機能の改善を図ります。
また、地域連携の観点から、紹介状持参で事前予約をお持ちの方、紹介状持参で当日受診された方については優先的に診察させていただく体制を整えていく予定にしております。受診の際は、ぜひ近隣の耳鼻咽喉科クリニックで紹介状を記載していただき、事前予約をお取りいただくことをお勧めいたします。
なお、耳鼻咽喉科を初診の方は、紹介状がなければ手術や当日の混み状況により、次回予約を取ってご帰宅頂くことがありますので、ご理解願います。
アレルギー性鼻炎
舌下免疫療法と外科治療を行っています。舌下免疫療法とは、従来の薬の治療と異なり、アレルギーの原因である抗原(スギ・ホコリなど)を少量から投与し、徐々に増量し、抗原に対して反応を弱める治療法です。舌の下に滴下する舌下免疫療法が保険適応となりました。現在は、ダニとスギ花粉に対する舌下免疫療法を行っています。治療は、長期間(3~5年)かかること、すべての患者さんに効果が期待できるわけではないことなど、いくつかの条件がありますが、ご希望される方は受診ください。また、外来手術での下鼻甲介焼灼や、入院手術での鼻閉改善手術(鼻中隔矯正術・下鼻甲介粘膜下骨切除)等にて外科的手術にて症状改善を行っております。
慢性副鼻腔炎・好酸球性副鼻腔炎・歯性上顎洞炎・真菌性副鼻腔炎
保存的治療で改善しない副鼻腔疾患については、低侵襲で効果的な治療を目指し、内視鏡手術を積極的に行っています。内視鏡手術は手術侵襲も少なく、入院期間も比較的短期間となります。また、喘息を合併する重症の副鼻腔炎の場合、難病指定の適応となることで、医療費負担が軽減される場合もありますので、ご相談ください。その際、近隣の耳鼻咽喉科クリニックから事前予約を取っていただくと待ち時間が短くなります。
めまい・耳鳴り
めまい・ふらつきの原因を検索し、わかりやすく説明できるように心掛けています。当科では、めまい検査が充実しており、大学病院レベルの検査を行うことができます。ENG(電気眼振記録法)・VEMP(前庭誘発筋電位検査)・蝸電図といった検査により、的確な診断に至ることができます。耳鳴りについても、聴力検査・耳鳴検査・画像評価を行い、器質性疾患を除外した後に、無難聴性耳鳴については認知行動療法を、難聴性耳鳴についてはTRT(Tinnitus Retraining Therapy)による音響療法を行っております。
嚥下障害
2013年に誤嚥性肺炎が死亡原因の3位になった頃より、嚥下障害が広く認知されるようになっております。部長山本は2008年頃より嚥下障害の治療の重要性に注目し今まで勤務してきた病院にて、手術や理学療法などさまざまアプローチを行って参りました。当院でも入院の上、呼吸・嚥下治療のために手術を行い、積極的に理学療法(特に歩行訓練)を行うことを大切にしております。嚥下障害の一端に栄養障害が関係することが多いため、入院にて栄養管理も行い、嚥下治療を行うこともあります。
声帯ポリープ・ポリープ様声帯、喉頭肉芽
炎症などで声帯の粘膜下に血腫が形成され、機械的な刺激が続くことで、ポリープが形成されます。声がすれ(嗄声)などが症状となることが多く、保存的治療で改善がなければ、顕微鏡下に切除する外科手術(顕微鏡下微細手術)を行います。また喉頭肉芽や胃食道逆流も声の出しにくさやのどのつまり感の原因になりますので、積極的に治療を行います。
扁桃疾患
習慣的に年に何回も扁桃炎を繰り返す場合、小児のイビキ・睡眠時無呼吸の場合や、扁桃の病巣感染症(掌蹠膿疱症、IgA腎症や胸肋鎖骨過形成症等)などに対して、ロ蓋扁桃摘出術(扁摘)を行っています。術後経過がよければ、術後3日程度での退院も可能です。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep apnea syndrome)は、高血圧、不整脈、脳血管障害等の原因や増悪因子になるといわれています。睡眠時の無呼吸や血中酸素濃度を測定する検査器機(アプノモニター)を貸し出し、検査結果を解析することで睡眠時の無呼吸の程度を判定します。重症例の保存的治療として、鼻にマスクを付け睡眠中の呼吸補助を行う方法(CPAP)を行います。小児の睡眠時無呼吸については、ほとんどの場合、扁桃肥大・アデノイド肥大が原因ですので、入院にて扁桃摘出術・アデノイド切除術を行っています。小児の睡眠時無呼吸症候群は、発達の遅れや成長障害を引き起こしますので、小児のイビキには注意が必要です。大人でも小児でもイビキがある場合には、ご相談ください。その際、近隣の耳鼻咽喉科クリニックから事前予約を取っていただくと待ち時間が短くなります。
突発性難聴・顔面神経麻痺
原因不明で急に耳が聞こえにくくなる病気である突発性難聴や顔の動きが悪くなる顔面神経麻痺という病気があります。当院では、突発性難聴・顔面神経麻痺についてのステロイド点滴は入院加療となります。当院では、ただステロイド点滴を行うだけではなく、蝸電図等のめまい検査を適宜実施することで、メニエル病などの疾患との鑑別を行い、診断治療の補助としています。
慢性中耳炎・真珠腫性中耳炎
慢性中耳炎による難聴や耳だれ(耳漏)の持続は日常生活の質を低下させます。手術治療による治癒を目指します。とくに、真珠腫性中耳炎は周囲の骨を溶かしていくことで、顔面神経麻痺やめまい、髄膜炎などを引き起こす原因になることがありますので、手術治療が必要です。当科では、重症の症例については、大阪大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科などから中耳手術専門の医師を派遣していただいて手術を行いますので、他院に転院することなく、当院で継続的に加療を行うことが出来ます。
補聴器外来
毎週金曜日に補聴器適合判定医・言語聴覚士・認定補聴器技能士による補聴器適合外来を行っています。補聴器は装用して直ちに聞こえるようになるわけではありません。そのため、試用期間をとり毎日装用しながら、定期的に補聴器適合検査(フィッティング)を行い、上手く調整を行って、補聴器を着けていることに慣れていく必要があります。補聴器外来では、状態が安定するまでのセットアップを中心に行っています。各種聴力検査を行ってからの予約となりますので、一般外来にお越しください。その際、近隣の耳鼻咽喉科クリニックから事前予約を取っていただくと待ち時間が短くなります。
当科の認定施設取得一覧
- 日本耳鼻咽喉科学会認定研修施設
- 補聴器適合検査基準施設
- ※当科では悪性腫瘍に対する加療を行っておりません。
頭頸部悪性腫瘍と診断された場合、大阪大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科や大阪国際がんセンター等に紹介とさせていただきます。 - ※難聴などの身体障害認定をご希望の方は、一般外来を受診ください。その際、近隣の耳鼻咽喉科クリニックから事前予約を取っていただくと待ち時間が短くなります。
現在実施中の臨床治験
臨床研究
参加中の臨床研究の情報を公開しています。
| 課 題 名 | 研究期間 | 情報公開文書 |
|---|---|---|
| 大手前病院の耳鳴順応療法(TRT)における音響療法の選択についての検討 | 2025年3月19日 ~ 2026年3月31日 | 情報公開文書.pdf |
| 難聴が疑われて大阪府下の精密検査機関・二次聴力検査機関を受診した児について の先天性サイトメガロウイルス感染症を含めた社会的調査 | 2025年5月22日 ~ 2029年3月31日 | 情報公開文書.pdf |
医師紹介
-
小幡 翔(おばた しょう)
役職 医員 -
山本 圭介(やまもと けいすけ)

役職 耳鼻咽喉科部長 主な
専攻分野日本耳鼻咽喉科学会認定専門医、日本耳鼻咽喉科眼科医耳鼻咽喉科専門研修指導医、日本嚥下学会、日本気道食道科学会、日本めまい平衡医学会、日本喉頭科学会、耳鼻咽喉科臨床学会、身体障がい者福祉法15条1項指定医 -
北山 一樹(きたやま いつき)
役職 医員 所属学会・
資格等日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会認定耳鼻咽喉科専門医、日本音声言語医学会認定音声言語認定医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会認定補聴器相談医、医学博士(大阪大学)
休診・代診情報
| 日付 | 曜日 | 担当 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診・代診情報はありません。 | |||
外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
北山 |
交替制 小幡 |
山本(圭) 北山 |
手術 |
小幡 山本(圭) |
| 午後 |
手術 |
耳鳴り・補聴器外来 小児耳鼻科外来 舌下免疫 |
- |
手術 |
耳鳴り・補聴器外来 |
- 診療科
- 特殊外来
- 部門
Access
最寄り駅❶大阪メトロ谷町線「天満橋駅」下車
1・3番出口より徒歩約5分
❷京阪電車「天満橋駅」下車徒歩約5分
❸JR東西線「大阪城北詰駅」下車徒歩約15分
住所〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-5-34
アクセス情報を見る